
越後長岡のシンボル 長生橋(長岡市)

長岡市のシンボルとして愛される「長生橋」
信濃川に架かっている橋長852mの「長生橋」は現在3代目で、平成19年には70歳を迎えました。「長生橋」は信濃川で分断されている長岡市の川東地域と川西地域を結ぶ重要な橋であるのはもちろんですが、毎年8月2日と3日に行われる大花火大会では「ナイアガラ」の名称で知られる「しかけ花火」が架かる橋としても有名で、長岡市のシンボルともなっています。
初代「長生橋」 〜川の真ん中で"ちょっと一杯"できた!?〜
長生橋が架かる以前は、川東地域(草生津)と川西地域(本大島)の間を「草生津の渡し(くそうづのわたし)」と呼ばれる渡し船によって往来をしていました。渡し船については、「………長岡の草生津の渡しは、川幅836.28mの大河で、大水の時は木や土石を流し又春雪解けの時は、堅い雪の固まりが激しく流れ、六隻の渡し船と人々は渡るに苦しむ事が度々あった………」という記録も残っているとおり、危険をともないました。また、時代が進むにつれて人も物資も多くなったため、円滑に運ぶことが難しくなってきました。信濃川の川西地域に住む人々にとっては、川東の長岡の町は魅力的であり、自由に往来できることが明治のはじめの川西地域の人々の願望でした。
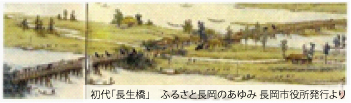 このようなことから、明治7年(1874年)12月三島郡岡村古新田(現長岡市緑町)の庄屋 広江椿在門(ひろえ ちかざえもん)氏は橋梁架設願を県に提出し、明治9年(1876年)4月に、いよいよ架橋がはじまりました。激流のなか突貫工事が行われ、着工から7カ月目の10月にめでたく、中州を挟んで東側の大橋と西側の小橋の2橋からなる木橋の初代「長生橋」が完成しました。
このようなことから、明治7年(1874年)12月三島郡岡村古新田(現長岡市緑町)の庄屋 広江椿在門(ひろえ ちかざえもん)氏は橋梁架設願を県に提出し、明治9年(1876年)4月に、いよいよ架橋がはじまりました。激流のなか突貫工事が行われ、着工から7カ月目の10月にめでたく、中州を挟んで東側の大橋と西側の小橋の2橋からなる木橋の初代「長生橋」が完成しました。
■マメ知識
・最初は龍が横たわるように見えるので、「臥龍(がりゅう)橋」と名付けられたようです。・「長生橋」の名前の由来は、「長生き」とも「長岡の"長"と草生津の"生"をとったとの話」とも諸説ありますが本当のところは分かっていません。
・建設費をまかなうための通行料を支払って、橋を渡っていました。
・新潟市の「万代橋」より10年早く、信濃川に架かる最初の橋でした。
・中州には一杯飲み屋・駄菓子屋・トコロテン屋がありました。
二代目「長生橋」 〜当時"日本一の長さの木橋"〜
 待望の初代「長生橋」でしたが、信濃川の洪水で、たびたび橋は破損・流失しました。災害は尽きることがなく、大正3年(1914年)8月の大洪水により橋の大半が流出し、県が新たな架橋に着手しました。
待望の初代「長生橋」でしたが、信濃川の洪水で、たびたび橋は破損・流失しました。災害は尽きることがなく、大正3年(1914年)8月の大洪水により橋の大半が流出し、県が新たな架橋に着手しました。但馬(現兵庫県)妙見山の杉材を使用して大正4年(1915年)11月に完成した2代目「長生橋」は、当時日本一の長さの木橋でした。しかし、またも風雨と洪水で部分流失を繰り返し、また損傷もひどく橋を渡るのが困難な状態になってしまったことから、3代目「長生橋」の建設へと移っていきます。
三代目「長生橋」 〜架橋から70年を過ぎ、現役の鋼橋〜
 昭和9年(1934年)から工事にかかり、途中イタリアとエチオピアの間で戦争が始まり、鋼材の値段が上がり、契約当時の価格と比較して5割近くも高騰するという思わぬ困難にもみまわれましたが、4年の歳月を経て昭和12年(1937年)10月に3代目となる現在の鋼橋の「長生橋」が誕生しました。
昭和9年(1934年)から工事にかかり、途中イタリアとエチオピアの間で戦争が始まり、鋼材の値段が上がり、契約当時の価格と比較して5割近くも高騰するという思わぬ困難にもみまわれましたが、4年の歳月を経て昭和12年(1937年)10月に3代目となる現在の鋼橋の「長生橋」が誕生しました。3代目「長生橋」は、ゲルバートラス橋と呼ばれるもので、昭和初期に採用されることが多かったようです。ほとんどが車社会化以前に整備されたものであったため、交通量増加に対応できず架替・撤去されたものも多いのですが、「長生橋」は約2万台/日の交通量をさばき、70歳を過ぎても現役で頑張っています。
「鋼橋」は鉄で出来ているため、「サビ」が発生すると部材が薄くなり橋の強度が低下します。そのため、「サビ」の発生を抑え、長く利用できるよう塗装をしています。この塗装は約10年に1回塗り替えが必要になりますが、「長生橋」の塗り替えに1回当たり4億円程度かかっています。
参考文献
http://www.pref.niigata.lg.jp/nagaoka_seibi/1194452153678.html

基本データ